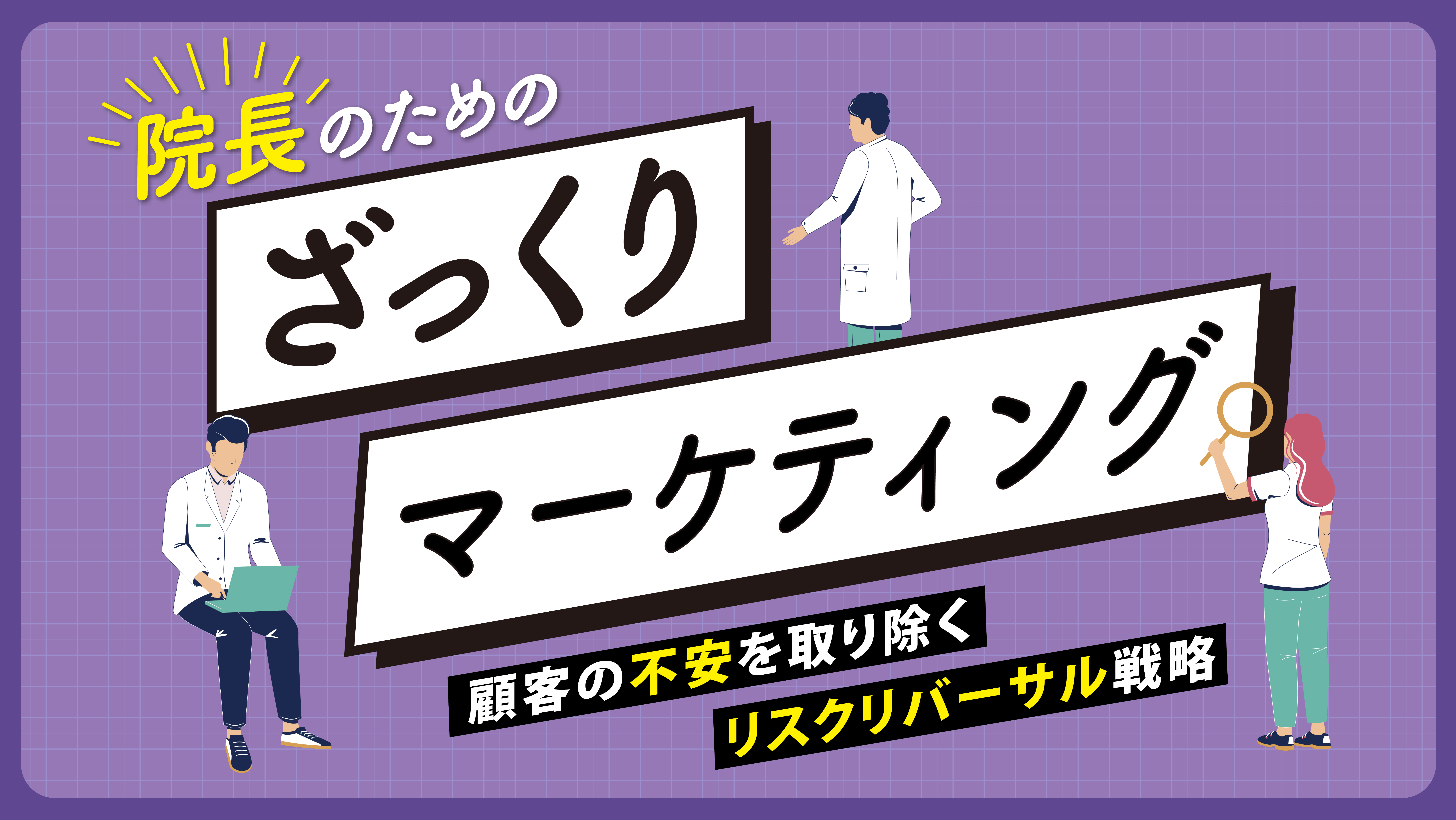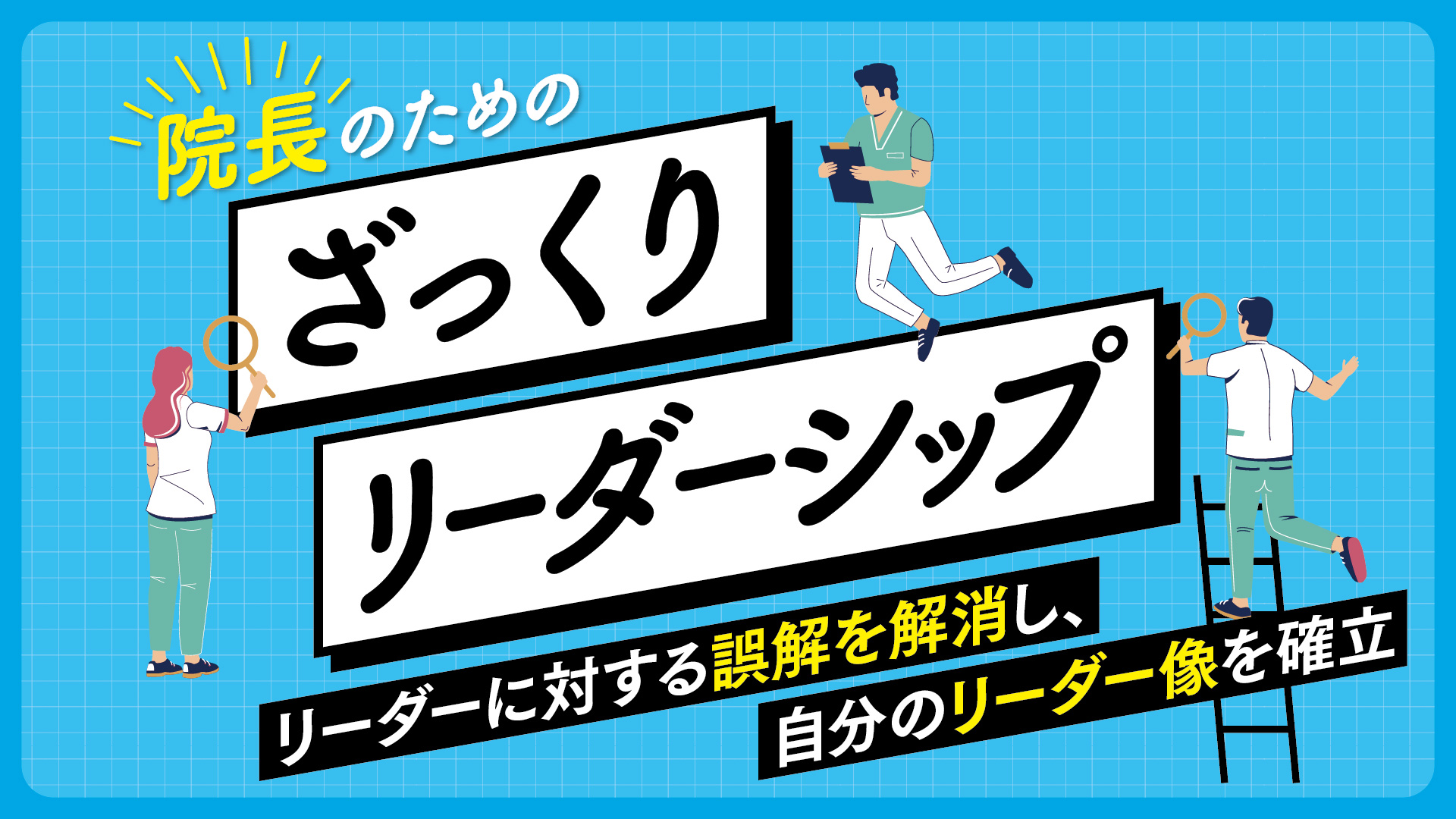#44 マネジメントは教わる事が第一歩?
2020年 4月 25日(土)
━━━━━━━━━━━━
最近自転車で通勤しており、とても健康的に過ごしています。
毎日同じ坂を登っていると、日々辛さが軽減されていき、成長を実感出来ていい感じです。
意外と自分の成長って実感出来ず、焦燥感が出たりしますよね。
さて、今日はマネジメントに関わる内容を皆さんに共有したいと思います。
先日、サッカー選手の本田圭祐さんと編集者の箕輪厚介さんとの対談を見ました。
そこで本田圭祐さんの考え方がめちゃくちゃ素敵で共感出来たので紹介したいと思います。
マネジメントに通ずるところだと思います。
─────
本田選手は幼稚園の頃から「ワールドカップで優勝する!」と言って、本田選手は昔からストイックであり、父親はスパルタ教育だったそうです。
箕輪さんが「なんで世界一のサッカー選手でもない父親の言うことを聞いていたの?」と言う質問をされてました。
この回答がめちゃ良かったです。
─────
その答えと言うのは
『自分が世界一の選手になりたい。ワールドカップで優勝したい』と言っているので、比較対象はその目標であり、父親ではない
というものでした。すごい幼稚園生ですよね。笑
さらに
父親も『それで世界一になれるのか』と厳しく言ってくるんですが、それは僕の夢に付き合ってくれているだけです。
『父親が嫌なら辞めたらいい』と言っていました。
すごい幼稚園生だなと思うとともに、むちゃくちゃ納得感が高い回答でした。
━━━━━━━━━━━━━━
どうマネジメントに通ずるのか
━━━━━━━━━━━━━━
先日紹介した面接の質問シートにも書いてあるのですが、僕はスタッフに必ず3つの質問をするようにしています。
それが
1. どのような社会人(獣医師や動物看護師)になりたいのか
2. その時いくら稼いでいきたいのか
3. そのために何をするのか
と言うものです。
これは故・野村監督が、監督する野球チームの選手全員にしていた質問らしいです。
ポイントは、
① 自分で考えさせる(考える)
② 自分の口で言わせる(言う)
という事だと思います。(本田選手の幼少期と同じですよね。)
何故かというと、『自責思考』になるからです。
ヒトって、何も意識しないと『他責思考』に流れてしまう生き物だと思っています。(自分も含めて)
他責思考というと、例えば
-
〇〇円でもお給料が増えれば嬉しい(会社が良い評価してくれ)
-
何をしたいかはわからないけど何者かになりたい(キッカケないかなあ)
-
会社(球団)がチャンスをくれない(自分は被害者)
こんな感じでしょうか。
自責思考は
-
市場価値を上げて給与交渉する
-
自分は〇〇になりたいから〇〇をする
-
自分の課題を見つけて、克服していく
となります。僕はこちらの方が、健全な考え方だし、成長しやすいと思っています。
━━━━━━━━━━
マネージャーの仕事は
━━━━━━━━━━
マネージャー(経営者や上司も)の役割は、本人の期待と現実のギャップをサポートする事だと思っています。
また、勝手に期待して、勝手にサポートや評価する事でもないし、努力をしたくない人を頑張らせることでもないと思います。(勿論、違うやり方もあると思いますが)
こう考えると、本田選手の父親は優れたマネージャーですし、本田選手が言っていた『自分で決めたことだから』と言う言葉はまさにその通りだと思います。
僕は起業して5年目から、3つの質問をスタッフにするようにしました。
と、同時に『信頼するけど、期待はしない』というスタンスに変えました。
ついつい自分にとって『都合の』良いスタッフを期待してしまう気がしたからです。
『期待して良いのは自分だけ』と思っているので、スタッフに
1. どのような社会人(獣医師や動物看護師)になりたいのか
2. その時いくら稼いでいきたいのか
3. そのために何をするのか
を教えてもらうようにしています。
そして、その目標に近づけているのか、何が足りないと思うのか、そのために何をサポートすれば良いのか、ということを
スタッフに教えてもらうことだと思っています。あとは、悩んでたら考え方を伝えたり、意見を求められれば伝えたり。
僕のマネジメントはそんな感じです。
ちなみに、もちろん明確な目標がなくても構いません(アドバイス出来るようになるため、この参考図書を読んでみます)。
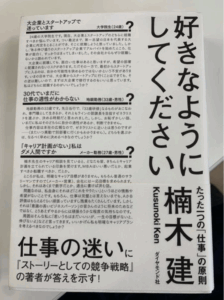
また、『自分には何ができるのか。何が足りないのか。』などを考えてもらい、自立した考えを持ってもらう事は必須事項だと思っています(うちでは)。
ただ、このマネジメントが正しいとは思っていません。1番のデメリットは、対応コスト(時間や感情など)がかかることです。一人一人違う対応するわけなので。
これと対になるのは、『みんなに同じ目標を持たせて、それに近づけているかを管理する方法』です。これまでの日本の多くの企業はこのスタイルでしたよね。モノサシが1つで良いので、対応コストは激下がりです。
ただ、型にハマれない人(僕みたいな)にとっては辛いだけだし、自分の考えには合ってないかなと思っています。
なので、うちの会社(動物病院)はよっぼどの事が無い限り、上限30名と決めています。
それが僕がマネージ出来る限界だと思うからです。
同じ考えのマネージャーが加入してくれて、機能するようであれば前言撤回するかもですが(^^)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
補足
当コラムは過去に限定コミュニティ『もしもMBAホルダーが動物病院を経営したら』内で配信していた記事のリバイバルです。
元臨床獣医師の豊田が、動物病院業界は『動物を笑顔にする人を笑顔にする人が足りない』という課題を持って起業、その後MBAホルダーとなり、満を辞して動物病院の経営を開始(2019年10月)しました。
このコラムでは、実際に動物病院を経営してみた気づきや取り組み、戦略戦術をノンフィクション経営物語として公開していきます。ビジネス的な考察や、他事業についても紹介していきます。